

※二人ともメガネっ娘なのは偶然ではなく、私の個人的な嗜好です。
モンハン世界では、数々のクエストを達成するハンターが群雄割拠しています(ちなみに、私の使用武器はガンスかスラアクでした。)し、異世界ナーロッパでも、冒険者の主人公が所属パーティから不遇な評価を受けて追放された状況から、別パーティで成り上がっていく再評価路線が多いですね。
さて、こうした物語では、ギルドとクエストの存在が不可欠です。そこで、今回はクエストの法的性質について考えてみましょう。
モンハン世界や異世界ナーロッパに共通するクエストの内容としては、薬草採取や飼い猫の探索、ゴブリンやリオレウスといったモンスターの討伐などがあり、手続としては、クエストを受注した後、クエストを達成すれば報酬が貰えるという形態がほとんどだと思います。
クエストの法的性質として考えられるのが懸賞広告(民法529条)、雇用(622条)、委任(643条)、請負(622条)、です。ひとつひとつ検討していきましょう。
1.懸賞広告

(懸賞広告)
第五二九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
懸賞広告については、警視庁の捜査特別報奨金制度が有名です。指名手配中(wanted)の犯人を見つけて捕まえたりしたらお金がもらえる制度です。
モンスターを討伐しても、クエストを受注していないとして、報酬を受け取ることができないとすると、懸賞広告の冒頭規定たる民法529条の「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず」という文言にそぐわず、クエストの法的性質を懸賞広告とは評価しがたいと考えられます。
たとえば、モンハンでは、リオレイアの討伐クエストを受注中に、乱入してきたリオレウスを討伐したとしても、リオレウス分の報酬は殆どもらえません。これは、モンハンのクエストが懸賞広告ではないことを示唆しています。
逆に、不特定多数人に対するモンスター討伐依頼や飼い猫の捜索願であれば、民法上の懸賞広告に該当しそうです。また、緊急性の高い討伐クエスト(緊急クエスト)であれば、誰でもよいので迅速に討伐する必要があるから、懸賞広告とすべきでしょう。
たとえば、異世界ナーロッパにおいて、無自覚チート主人公が偶然にも当該モンスターを倒して、「またオレ何かやっちゃいました?」(=懸賞広告の存在につき善意)となっても、依頼者から報酬をもらうことができるわけです。典型例としては、このすばのキャベツ討伐クエストでしょうか。

2.雇用
(雇用)
第六二三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用=労働とは、①会社の指揮命令を受けて仕事し(使用従属性)、②労働時間に応じて賃金が支払われる(経済的従属性)形態です。労働法では「労働者」性がそのまま労働法(労働契約法、労働基準法、労働組合法など)の適用範囲を画しますね。
本件では、ギルドの指揮命令を受けつつモンスターを狩猟しているわけでもなければ(①)、モンスターの狩猟時間に応じて報酬が貰えるわけでもない(②)ので、クエストの法的性質を雇用と評価するのは難しいと思われます。常識的に考えて、ハンターや冒険者を労働者と考えるのも変ですし。
実際にモンハンでも、制限時間内にモンスターを討伐できなかった場合、報酬はもらえません。
3.準委任vs請負
(委任)
第六四三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(請負)
第六三二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
※モンスター討伐は法律行為でないから、準委任(656条)を考える。
準委任と請負の区別はおおむね以下の観点から判断するのが普通です。
①結果債務か手段債務か
②自己執行義務(善管注意義務の一環644条)を負うかby当事者間の信頼関係に基づくか
③有償契約か無償契約か
①について、結果債務はある結果の実現(成果物の引渡しが典型)を内容とする債務であり、手段債務はある事務の処理を内容とする債務(結果の実現は重視されない)をいうと考えてよいです。結果債務であれば請負になりやすく、手段債務であれば準委任になりやすいです。
採取系クエストについては、薬草やハチミツの納品が達成条件となっていますから、特定の物品の納入という結果の実現が債務の内容になっており、結果債務に当たると考えられます(請負になりやすい)。
討伐系クエストについては、モンスターの死骸の納入という結果の実現までは要求されておらず、モンスターを討伐すればクエスト達成になると解すると、モンスター討伐という事務の処理が債務の内容となっており、手段債務に当たると考えられます(準委任になりやすい)。モンスター討伐を結果の実現とも評価しえますが、何か成果物の納品を求めているわけではないので、請負よりは準委任に傾くと思います。
②について、自己執行義務とは、債務者が負う、自分で債務を履行しなければならず、第三者に委託してはならないという義務をいいます。この義務を負うべきと解すると準委任になりやすく、負わないと解すると請負になりやすい(ex.多重請負)です。
採取系クエストについては、薬草などを誰が採取しても、依頼者としては薬草が入手できれば満足するのですから、冒険者・ギルド間の信頼関係は大して重要ではなく、冒険者は自己執行義務を負わないと考えられます(請負になりやすい)。採取系は最低ランクの代表的なクエストであり、実質誰でも受注できますからね。クエストの交換も許されると考えられます。
討伐系クエストについては、異世界ナーロッパにおいて、E~Sランク、銅(カッパー)~アダマンタイトのようにランク分けし、ランク別のクエストが用意されていることから、誰でもモンスターを倒せばよいのではなく、ギルドは実力に対する一定の信頼に基づいて冒険者に依頼していると考えられます。そうすると、冒険者・ギルド間の信頼関係は重要ですから、冒険者は自己執行義務を負うと考えられます(準委任になりやすい)。ゆえに、クエストの交換は許されません(無職転生1期11話参照)。
③については、確認がでらに、無償契約であれば準委任に該当します(643条の文言参照)。もっとも、有償契約だからといって、直ちに請負になるわけではなく、委任になることもあります。
クエスト達成には報酬が支払われますから、無償契約ではありません。
4.結論
以上のように、採取系クエストについては、結果債務であり、かつ自己執行義務を負わないと解されるため、請負に当たると評価できます。その一方、討伐系クエストについては、手段債務であり、かつ自己執行義務を負うと解されるため、準委任に当たると評価できます。
また、 不特定多数人に対するモンスター討伐依頼や飼い猫の捜索願であれば、民法上の懸賞広告に該当しそうです。緊急クエストについても、緊急性の高さゆえに、懸賞広告とすべきでしょう。もっとも、緊急性が高くないとともに、パーティ間でモンスターの討伐争いが多発すると予想されるクエストについては、他パーティによる不当な横取りを防ぐため、懸賞広告ではなく、準委任にすべきでしょう。

おまけ 討伐系クエストの二重発注(ダブルブッキング)について
ギルド受付嬢の手違いで、1個の討伐系クエストを2組以上のパーティが受注してしまった場合、ギルドの損害賠償責任はどうなるんでしょう。そうならないように、排他制御すべきでしょうね()








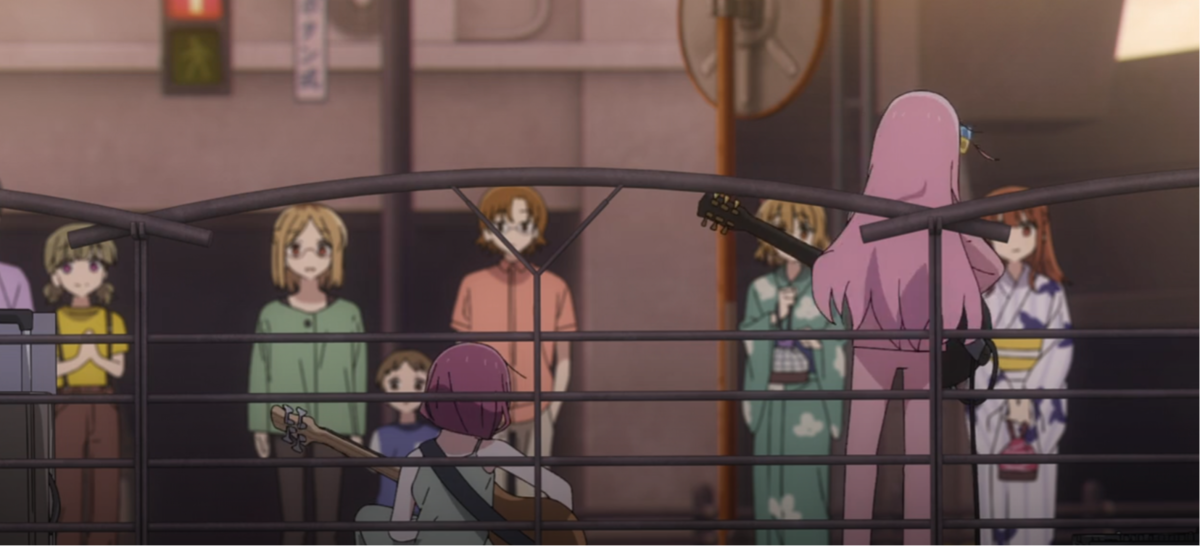



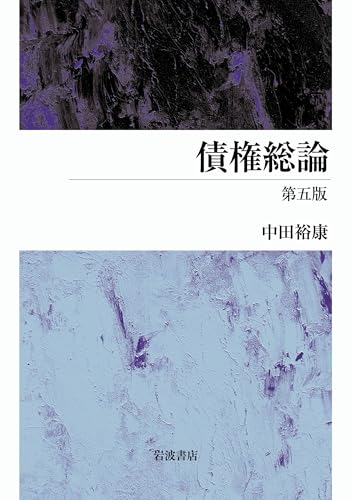

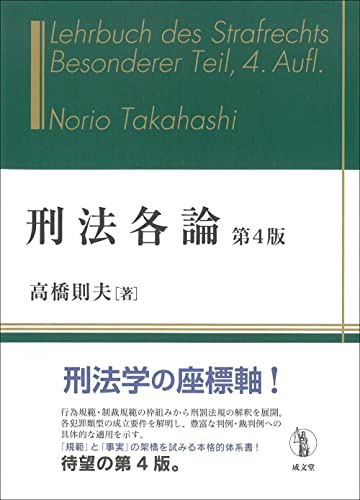



![完全講義 民事裁判実務[基礎編]─要件事実・事実認定・民事保全・執行─ (完全講義シリーズ) 完全講義 民事裁判実務[基礎編]─要件事実・事実認定・民事保全・執行─ (完全講義シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51w8aGFjAbL._SL500_.jpg)



